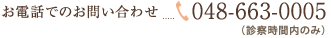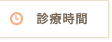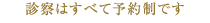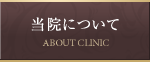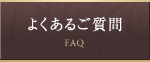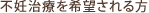婦人科
婦人科
子宮がん検診
子宮の入り口(子宮頚がん)、子宮の中(子宮体がん)の細胞の検査です。必要に応じて組織検査などの精密検査も行います。
卵巣がん検診
超音波を使って卵巣が腫れていないかをチェックします。一回の検査ではっきりしない場合には時期を変えてもう一度見せていただくこともあります。
結果により必要があれば採血にて腫瘍マーカーを調べたり、専門の医療機関へご紹介のうえ、MRI検査を行います。
異常が疑われれば専門の医療施設をご紹介いたします。
月経不順
いわゆる生理不順です。
多くは排卵が起こっていなかったり、不規則であるために生理が不順になります。引越しや転職などによるストレス、体重の急激な変動、一部の精神安定剤がきっかけで排卵しにくくなることもあります。
基礎体温表、血液のホルモン検査、超音波検査などで原因を調べます。
性行為感染症
性行為によって感染する病気です。
婦人科的にはクラミジア、淋菌、ヘルペスなどがあります。最近では咽頭(のど)からこれらの菌が発見されることがあります。
血液検査あるいは子宮の出口をこすった検体やうがいをした液を調べる方法で検査します。
子宮筋腫
子宮にできる良性の腫瘍で、30歳以上のご婦人の約1/3にあるともいわれています。
月経困難症、月経過多症、貧血、不妊、流産の原因になることがありますが、検診ではじめて発見される無症状の例も少なくありません。
ほとんどの場合、超音波検査で比較的簡単に診断することができますが、必要に応じて専門の医療機関へご紹介のうえ、MRI検査を行います。
発生部位や大きさ・自覚症状の有無・患者さんのご年齢・妊娠を望まれるかどうかなどにより治療方法を決定するのが一般的です。
治療にはホルモン療法(注射または点鼻薬)、手術、子宮動脈塞栓術(UAE)や、集束超音波治療(FUS)などがあります。
子宮内膜症
本来は子宮の内側にのみある子宮内膜の組織が子宮の表面や筋肉の中、卵巣にできてしまう病気です。月経困難症、性交時痛、腰痛、不妊症の原因になることがあります。
内診や超音波検査、血液検査で診断しますが中には腹腔鏡検査をしてはじめて発見される場合もあります。
自覚症状の有無・患者さんのご年齢・妊娠を望まれるかどうかなどにより治療方法を決定するのが一般的です。
治療にはホルモン療法(ピルや黄体ホルモンの内服、点鼻薬や注射による治療)、手術などがあります。
更年期障害
閉経の前後5年間を更年期といいます。この時期、卵巣の働きが弱まるためにおこる様々な不快な症状を更年期障害と呼びます。
症状は患者様によって異なりますが、代表的なものはのぼせ、イライラ、発汗、肩こりなどの自律神経失調に伴う症状となります。漢方薬やホルモンの補充により治療するのが一般的です。
またこの時期、卵巣のホルモンの減少により萎縮性膣炎(おりものが増えたり外陰部がしみて痛い)や骨粗しょう症(骨がもろくなる)などの特有の病気がおこることもあり注意が必要です。プラセンタ製剤(メルスモン)で改善する患者様もいらっしゃいます。
月経前緊張症(PMS)
生理開始前に起こる精神的、身体的症状で生理がはじまると消失していくものを言います。いらいらやのぼせ、頭痛、怒りっぽくなるなどの症状があります。
漢方薬や低容量ピルである程度症状を緩和することが可能です。